先日、家でニュースを見ているともう沖縄は梅雨に入ったと言っていました。
毎年、梅雨に入ると「頭が重い」「身体がだるい」「やる気が出ない」といった相談がぐっと増えます。そうした不調に悩む方の多くが、実は「低気圧」による影響を受けています。
でも、病院で検査しても「異常なし」と言われる…そんな経験はありませんか?
それもそのはず。こういった症状の多くは「自律神経の乱れ」が原因で、整体や生活習慣の見直しで改善することが多いのです。
今回は、整体師の視点から、低気圧によって起こる体調不良のメカニズムとその対処法をわかりやすく解説していきます。東洋医学的な視点も交えながら、あなたが梅雨のストレスを乗り越えるヒントをお伝えします。
1. なぜ梅雨や低気圧で体調を崩すのか?
⛈ 気圧の変化と体へのストレス
梅雨の時期に体調を崩す人は多いですが、その大きな原因が「気圧の変化」です。低気圧になると空気中の酸素濃度が下がり、副交感神経が過度に働くことで、次のような症状が出やすくなります。
- 頭痛
- 倦怠感
- めまい
- 肩こり
- イライラ・不安感
- 古傷の痛み
🌧 湿気による“体のだるさ”
湿度が高くなると、汗の蒸発がうまくいかず、体温調節が乱れます。また、体内に「水分」がたまりやすくなるため、「むくみ」や「冷え」「関節の痛み」などが現れることもあります。
整体的には、これを“循環の停滞”と捉えます。
2. 自律神経の乱れが引き起こす梅雨の不調
🧠 自律神経とは?
自律神経は、私たちの意識とは無関係に働いている神経で、内臓の動き・血圧・呼吸・体温調節などをコントロールしています。
- 交感神経:活動・緊張モード
- 副交感神経:休息・リラックスモード
気圧の変化や天候不順はこのバランスを乱す大きな要因になります。
☔ 気象病・天気痛という概念
最近では「気象病」「天気痛」といった言葉が広く知られるようになりました。これは、気圧の変化や湿度の影響で悪化する慢性症状のことです。
代表的な症状には次のようなものがあります。
- 偏頭痛・緊張型頭痛
- 首・肩こり
- めまい・耳鳴り
- 腰痛や関節痛の悪化
- 不眠
- 胃腸の不調(便秘・下痢・食欲不振)
3. 東洋医学で見る“梅雨の不調”〜湿邪と脾の弱り
🌿 湿邪の特徴
- 重くて停滞しやすい性質
- 身体の水分代謝を妨げる
- 消化器系(脾・胃)を弱らせる
- むくみ・だるさ・関節痛を引き起こす
💡 湿邪に負けない体づくりのカギは「脾」
「脾(ひ)」は、東洋医学で消化吸収や水分代謝に関係する臓器です。湿気が多いと脾の働きが低下し、「水はけの悪い体」になりやすくなります。
湿邪を追い出すには、以下のようなケアが大切です。
- 胃腸に負担をかけない食生活
- 身体を冷やさない習慣
- 適度な運動で代謝を上げる
4. 整体師が教える“梅雨ストレス”解消のアプローチ
🔧 骨格の歪みを整えて自律神経をリセット
自律神経は背骨を通って全身に分布しています。そのため、背骨や骨盤の歪みは自律神経の乱れを引き起こす大きな要因です。
整体では、特に次の部分を重点的に調整します。
- 首(頸椎)
- 胸椎
- 腰椎
ゆがみを整えることで、血流・神経伝達・ホルモンバランスがスムーズになり、不調が和らぎやすくなります。
👐 筋膜リリースで水の巡りを助ける
湿邪の影響を受けると、筋肉や筋膜がねばりつくように硬くなることがあります。整体ではやさしく筋膜をリリースして、“水の巡り”を改善します。
5. 自宅でできる梅雨ストレス対策6選
- 白湯を飲んで内臓を温める
- 湿を追い出す食材を取り入れる
- ◎:はとむぎ、しそ、しょうが、黒豆、みょうが
- △:冷たい飲み物、生野菜、甘い物
- ぬるめのお風呂にゆっくり入る
- 耳を回して自律神経を整える
- 深呼吸+肩甲骨ストレッチ
- 朝日を浴びる
6. 梅雨ストレス対策におすすめの整体通院のタイミング
- 月1〜2回のメンテナンス
- 頭痛・倦怠感が出始めたら早めのケア
7. まとめ 〜 梅雨の不調は“体からのサイン”
梅雨になると調子が悪い——それはあなたの体が自然の変化に反応している証拠です。
無理に「気のせい」と我慢せず、整体・セルフケア・生活改善を通じて、身体の声にやさしく応えてあげてください。
「雨の日でもスッキリ起きられる」「朝から元気に動ける」——そんな体は、ちょっとした習慣の積み重ねで作れます。
あなたもぜひ、この梅雨を“心地よく過ごすきっかけ”にしてくださいね。
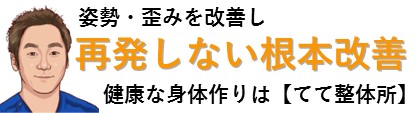





お電話ありがとうございます、
てて整体所でございます。