ある日突然、腕が上がらない。
夜中にズキズキ痛くて眠れない。
シャツを脱ぐだけで激痛が走るーーー。
このような症状を経験して、「もしかして五十肩?」と思った方は少なくないはず。中高年に多く見られる「五十肩」は、年齢を重ねれば誰でもなる可能性がある身近な疾患です。しかし、「なぜ五十肩になるのか?」「肩の中で何が起こっているのか?」といった根本的な仕組みや原因については意外と知られていません。本記事では、五十肩の発症メカニズム・原因・リスク要因・予防法までをわかりやすく解説します。五十肩に悩んでいる方や、予防したい方にとって、身体の理解を深めるきっかけになれば幸いです。
五十肩とは?正式名称と基本の理解
「五十肩」は通称であり、医学的な正式名称は「肩関節周囲炎(かたかんせつしゅういえん)」と呼ばれます。その名の通り、肩関節の周囲の組織(腱、靭帯、関節包など)に炎症が起こる病気です。
主な症状は以下の通り:
・肩の動きに制限がでる(腕が上がらない、回らないなど)
・動かしたときの鋭い痛み
・安静にしていても痛む(特に夜間)
・服の着脱や洗髪など、日常動作に支障が出る
40代後半から60代に多く発症するため「四十肩」「五十肩」と呼ばれていますが、年令による厳密な違いはありません。どちらも同じ病態を指します。
なぜ五十肩になるのか?【3つの主なメカニズム】
五十肩の発症メカニズムは、完全に解明されていない部分もあるため「原因不明」と言われることもありますが、近年の研究や臨床経験から、以下の3つが有力とされています。
1・肩の関節包の拘縮(こうしゅく)
五十肩の本質は肩関節を包んでいる「関節包」が硬くなり、動かなくなることです。
これを「拘縮(こうしゅく)」といいます。
肩関節の構造とは?
肩関節は、上腕骨(腕の骨)と肩甲骨によって構成され、関節の周りを「関節包」と呼ばれる袋状の膜で覆われています。
この関節包は、肩の広い可動域(腕を360度動かせる)を支える重要な存在です。
なぜ拘縮が起こるのか?
加齢や負荷の蓄積によって、関節包に微細な炎症が起こり、その修復過程で線維化(硬くなる現象)が進みます。
これにより関節包が縮んでしまい、動きが制限され、痛みが出るのです。
2・腱板(けんばん)の変性と癒着
肩の筋肉と骨をつなぐ腱の集合体である「腱板(トーテーターカフ)」は、五十肩の発症に大きく関係しています。
腱板は年齢とともに劣化する
腱板は日常生活で酷使されやすく、40代以降になると自然に変性(劣化)しやすくなります。変性が進むと、小さな断裂や炎症が起こり、炎症が長引くと、周囲の滑膜や関節包が更に硬くなり癒着を起こします。癒着が起こると可動域が著しく制限され、痛みも持続します。
腱板炎と五十肩の違いは?
腱板自体の炎症や断裂は、五十肩と症状が似ていますが、実際には別の疾患として扱われます。ただし、五十肩の方の多くは、腱板の変性も併発していることが多いため、無視できない要因です。
3・血流の低下と組織の老化
肩関節周囲の組織は、加齢によって血流が悪くなりやすい場所です。血流が悪くなると、組織の修復が遅れたり、炎症が長引いたりすることで、慢性化しやすくなります。また、筋肉や腱の柔軟性が失われると、些細な動作で肩周りに負担がかかるため、炎症→痛み→動かせない→更に硬くなる、、、。という悪循環に陥りやすいです。
なぜ「50代前後」に多いのか?
五十肩はなぜ、中高年層に集中して発症するのでしょうか?そこには以下のような要因が関係しています。
1・加齢による組織の変性
先述したように、40代以降になると腱板や関節包が加齢による変性(硬くなる・傷つきやすい)を起こしやすくなります。
2・長年の負荷の蓄積
若い頃からのスポーツ歴や、日常の姿勢の癖、片側の方ばかり使う動作(荷物を持つ・利き腕を使う)が、数十年にわたって蓄積し、肩のダメージを与え続けているのです。
3・ホルモンバランスの変化
特に女性では、更年期に入ることで(エストロゲン)の分泌が減少します。エストロゲンは炎症を抑えたり、筋肉・関節を柔らかく保つ働きがあるため、減少すると肩関節がこわばる安くなるのです。
五十肩と他の方の疾患の違い
五十肩と混同されやすい疾患には、以下のようなものがあります。
| 疾患名 | 主な症状 | 特徴 |
| 腱板断裂 | 肩をあげられない・力が入らない | 外傷や使いすぎが原因・手術が必要な場合もあり |
| 石灰沈着性腱炎 | 突然の激しい痛み・熱感あり | 肩に石灰がたまる・レントゲンで診断可能 |
| 頚椎症 | 肩だけではなく腕や指にしびれ | 神経の圧迫が原因・首の異常が関連 |
五十肩はこれらとは異なり、徐々に肩の動きが制限され、長期間にわたり痛みが続くことが特徴です。五十肩かな?と思っても違う疾患が原因のこともあるので、まずは整形外科でレントゲンやMRIなどの画像検査をおすすめします。
五十肩の発症を促すリスク要因
五十肩になりやすい人にはいくつかの共通点があります。
1・姿勢の悪さ
姿勢が悪いと、肩の位置がズレて関節包や腱にかかる負担が増えます。
2・デスクワークやスマホの長時間使用
長時間の同じ姿勢、特に前かがみで肩が内側に巻いた姿勢は、肩関節の可動域を狭め、拘縮を招きます。
3・運動不足
肩関節は「使わなければどんどん硬くなる」部位です。日常的に肩を大きく動かす機会が少ないと、関節の柔軟性が失われていきます。
4・糖尿病や甲状腺疾患
糖尿病やホルモンの異常があると、組織の代謝や修復機能が低下し、五十肩のリスクが高まることがわかっています。
五十肩は自然に治るのか?
五十肩は一般的に「自然治癒することが多い」と言われますが、その過程には長い時間がかかりますし、癒着がある五十肩は特に改善に時間がかかります。一般的に進行は以下の3段階で進みます。
【1】急性期(痛みの強い時期):~3ヶ月
安静にしていてもズキズキ痛む。夜間痛が強い。
【2】拘縮期(動かしにくい時期):3~9ヶ月
痛みは少し落ち着くが、肩が固まり動かしにくい。
【3】回復期(少しづつ動く時期):半年~1年半
可動域が徐々に戻り、日常生活も楽になる。
すべての段階を経て完治までには平均1~3年かかるケース多く、その間に生活の質が大きく下がることがあります。
発症を防ぐには?今日からできる予防策
五十肩を完全に防ぐことは難しいですが、日常の工夫でリスクを減らすことはできます。
◆肩甲骨を意識して動かす
・肩甲骨をゆっくり寄せる→離す を10回
・壁に手をついて、腕を上げるストレッチ などを行う
◆姿勢改善(座り方・立ち方)
・背筋を伸ばして肩が前に出ないように意識する
・デスクワーク中は定期的に休憩し、腕を回す
◆肩を冷やさない
・冷えは血流を悪化させ、肩周りの筋肉を硬くします。冷房対策や肩温めグッズを活用しましょう。
◆運動習慣をつける
・ウォーキング・ヨガ・軽い筋トレなど、肩関節を使う全身運動が有効です。
まとめ:五十肩は「老化現象」ではなく「身体のサイン」
五十肩は単なる老化現象ではなく、日常生活や体の使い方のクセが積み重なって生じる「身体からのサイン」です。肩の構造を理解し、早期に対応することで、進行を防いだり、回復を早めることができます。そして何より、肩の健康を意識することは、姿勢改善・血流改善・自律神経の安定など全身の健康にもつながるのです。
「五十肩かも?」と感じたときは我慢せず、まずは整形外科で画像診断を受け、あなたが信頼できる整形外科・リハビリ・整体で適切なケアを受けましょう。予防にも、回復にも、”正しく知ること”が最も大きな武器になります!
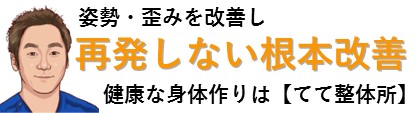





お電話ありがとうございます、
てて整体所でございます。